火事のあった家の売却を解説!価格への影響や告知義務、売却方法は
こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
「火事で家が損傷してしまったけれど、売却できるのだろうか?」
「火災のあった家は値段が下がってしまうのかな...」
「買い主に火事があったことを伝えなければいけないの?」
このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
過去に火事が発生した不動産でも売却は可能ですが、火災の程度や状況によって売却方法や価格に影響が出ることがあります。
今回は、火事のあった家を売却する際のポイントや注意点を詳しく解説します。
告知義務や価格への影響、効果的な売却方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

火事のあった家を売却したい!売却価格への影響はある?
火事のあった家の売却相場は、通常の家の売却価格の50〜80%ほどとなるのが一般的です。
火事の事実は、買い主にとって「その物件に住む」ことへの心理的な抵抗感を生む可能性があります。
減額の割合は、火事の規模や被害の程度によって変わります。
例えば、火災によるダメージが軽微(ボヤ程度)で適切に修繕されている場合は、価格への影響がほとんどないこともあるでしょう。
キッチンの天井が少し焦げた程度であれば、リフォームをして痕跡がなくなれば、相場と同等の価格で売れる可能性もあります。
一方、家が半焼や全焼した場合は、建物の価値が大きく下がることが考えられるでしょう。
特に、火災によって人が亡くなった場合は、売却価格に大きな影響を及ぼします。
このような不動産は「心理的瑕疵(かし)」があると見なされ、建物を取り壊したり建て替えたりしても、買い手が慎重になる傾向があります。
そのため、売却方法を工夫することが重要です。
火事のあった家の売却には告知義務がある
火事のあった家を売却する際には、買い主に対して火災の事実を伝え、正確に説明する義務があります。
理由としては、前のブロックで触れた通り、火事があった事実、特に火災によって人が亡くなった場合(事故物件)は、「心理的瑕疵」としての影響が大きいためです。
心理的瑕疵とは、多くの人が「そこに住むことに抵抗を感じる」と思うような物件の問題を指します。
なお、瑕疵には心理的瑕疵以外にも、雨漏りやシロアリ被害などの「物理的瑕疵」、近隣に葬儀場や墓地などがある「環境的瑕疵」など、いくつか種類があります。
「瑕疵について知っておきたい」という方はぜひ、「不動産売却は告知義務がある!告知が必要な瑕疵や売却時の注意点も」のコラムもあわせてご参照くださいね。
告知するかどうかは自己判断しないことが大切
「ボヤ程度の火事であれば、心理的瑕疵にはならないのでは?」と思われるかもしれません。
実際、火事の規模や被害の程度によっては、告知の義務が発生しない場合もあります。
とはいえ、「ボヤ程度だから」「数十年前のことだから」「誰も気にしていないだろう」と、売り主だけの考えで「告知不要」と判断するのは避けるべきだといえます。
心理的な抵抗感の度合いは人それぞれ感じ方が異なり、具体的な経過年数や、規模の定義が明確に決まっていないため、「どのような火災なら心理的瑕疵にあたるか」といった判断は難しいからです。
また、過去の火災について覚えている人がいる可能性もあります。
そのため、売り主が告知をするかどうか自己判断せず、売却を依頼する不動産会社に火事の内容を伝え、適切な判断を仰ぐことが重要です。
告知しないと「契約不適合責任」を問われるリスクがある
物件に瑕疵があるにもかかわらず、買い主に告知しなかった場合、後日トラブルとなり、「契約不適合責任」を問われるリスクがあります。
契約不適合責任とは、売買契約の対象となる物件に、契約内容と適合しない部分(瑕疵)があった場合に、売り主が負う責任のことです。
例えば、買い主から「火事があったことを知っていたら買わなかった」などと主張され、契約解除や損害賠償請求を受ける可能性があるのです。
トラブルを防ぐためにも、火事のあった家を売却するときは「この程度なら言わなくても大丈夫」と自己判断せずに、売却を依頼する不動産会社に必ず確認しましょう。
なお、火事のあった家に限らず、長期間放置された空き家にもさまざまなリスクがあるため、適切な管理と対策が求められます。
空き家の活用方法や解決策については、「空き家放置はリスクがたくさん!活用方法やすぐできる解決方法をご紹介」のコラムもぜひご覧ください。
火事のあった家を売却する方法
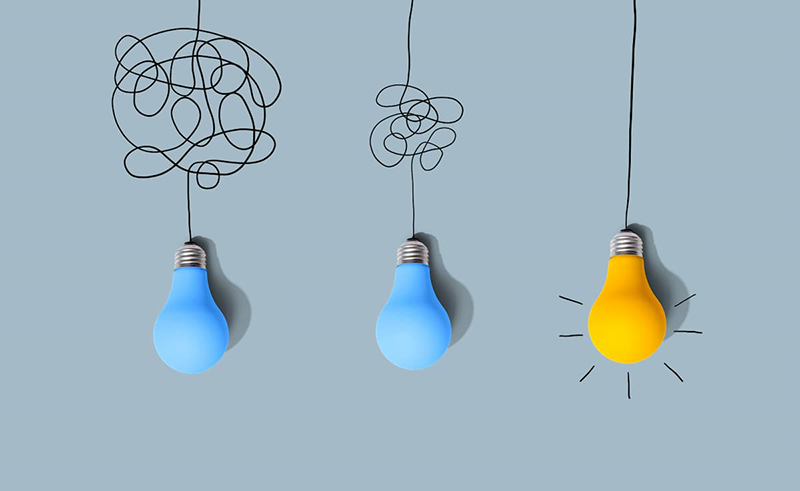
火事があった家は、買い手の心理的な抵抗感から売却が難しくなる傾向があります。
しかし、適切な売却方法を選ぶことで、スムーズに売却できるだけでなく、市場相場に近い価格での取引も期待できるでしょう。
ここでは、「どうすればスムーズに売れるか」「どうすれば少しでも相場に近い値段で売れるか」という観点から、効果的な売却方法をご紹介します。
方法1|火事のあとを適切に修繕してから売却する
物件の見た目や機能を回復させてから売り出すと、買い主の心理的な抵抗感を大幅に軽減できる可能性があります。
特に、火災保険に加入している場合には、保険を利用して自己負担を最小限に抑えながら修繕できるというメリットがあります。
物件の外観や内装が改善され、「火事があった」という印象が薄れれば、意外にも「火事の事実は気にしない」「ボヤ程度なら問題ない」と考える買い主も多いでしょう。
また、立地条件などが良ければ、相場に近い価格で、スムーズに売れる可能性も高まります。
ただし、修繕して痕跡がなくなったとしても、告知義務がなくなるわけではありません。
火事による修繕した事実は、不動産会社に正しく伝え、適切な告知の判断を仰ぐことが重要です。
方法2|ホームインスペクションを受けてから売却する
「火事のあった家に住んでも安全なのか」といった買い主の不安を解消するために、第三者機関による住宅診断(ホームインスペクション)を活用する方法があります。
診断には費用がかかるものの、専門家による客観的な診断結果があれば、売り主の説明だけでは伝わりにくい安全性を証明できるため、買い主の安心感につながります。
ホームインスペクションでは、住宅診断士が建物の状態を専門的に調査し、報告書を作成します。
この報告書を買い主に提示することで、信頼感を高めることができます。
また、第三者の専門家による「安全性の証明」があることで、「第三者の専門家の証明があるなら安心」という心理が働き、価格交渉時の値引き幅を抑えられる可能性も高まるでしょう。
方法3|更地にして売却する
建物の損傷が大きく修繕費用が高額になる場合や、土地自体の価値が高い立地では、建物を解体して更地にしてから売却する方法が有効です。
更地にすることで、火災の物理的な痕跡を完全に取り除けるため、「新しく家を建てたい」と考えている買い主にもアピールできます。
また、買い主にとっては、解体費用の負担が不要になる点もメリットです。
特に駅近や好立地の場合は、更地にすることで土地の価値を最大限に引き出せる可能性も高まるでしょう。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 解体費用は売り主の負担になる
- 住宅用地の固定資産税軽減措置(住宅用地特例)が適用されなくなり、固定資産税が上がる可能性がある
売却までに時間がかかると税負担が増してしまうため、更地にした後は速やかに売却することが大切です。
不動産会社とよく相談したうえで決断しましょう。
方法4|「不動産買取」を利用する
「とにかく早く売却したい」「修繕費用を捻出できない」「相続した火災物件を早く処分したい」といった場合には、不動産会社に直接売却する「不動産買取」を検討してみましょう。
不動産買取は、一般の買い主を探す手間や時間を大幅に短縮できるため、売却までの速さと確実性を重視する場合に適した方法です。
多くの場合、修繕せずそのままの状態で買い取ってもらえることが多いので、追加費用がかかる心配もありません。
ただし、買取価格は一般的に市場価格の7割程度になることが多く、火災物件の場合はさらに低くなる可能性があります。
不動産会社によって買取価格に差があるため、複数社に査定を依頼することが重要です。
買取を検討する際には、価格だけでなく、担当者の対応の丁寧さや信頼性も比較検討しましょう。
ただし、買取価格は一般的に市場価格の7割程度になることが多く、火災物件の場合はさらに低くなる可能性があります。
火事のあった家は物件の状態に応じた売却方法の工夫が大切
火事のあった家の売却には、通常の不動産とは異なる課題があります。
火災の程度によっては売却価格に影響が出ることがありますが、適切な対策を講じることで、価値の下落を最小限に抑えることが可能です。
重要なのは、火災の事実を買い主に正確に告知することです。
告知義務を怠ると、後のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
火事のあった家の売却方法としては、修繕して機能を回復させる、ホームインスペクションで安全性を証明する、更地にする、不動産買取を利用するなど、物件の状況に合わせた選択が大切です。
専門家のアドバイスを受けながら最適な売却戦略を立てることで、火事のあった家でもより良い条件での売却が期待できるでしょう。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

那須塩原店 土屋 清
その他の不動産売却の基礎知識










